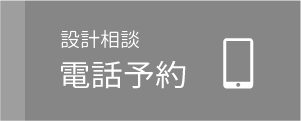余白について
このサイトは 「The Gran(ザ・グラン)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

余白は何もない空間としての他に、なにかが生まれる場所、契機としてもとらえられているようです。ザ・グランの他、現代アーティスト、音楽家、美術評論家が「余白」をどうとらえるかについて取り上げました。
余白とはなにもないスペースを指すことが多いですが、それは余っているもの、または不要なものではなく、必要なものとして意図的に設けられるという意味が「余白」という言葉には込められているように感じます。
住まいづくりにおいても「余白」は、強く意識する大切なテーマです。あらかじめ用途が決まっていない空間を余白としてもうけることで、生活にゆとりにつながることがあります。
余白を生かすも殺すも生活者次第のところもありますが、それを見越したうえでオーダー未満のニーズをとらえて実現していくことは建築家・設計士の経験に裏打ちされたセンス・感性によります。
岐阜の高級注文住宅ビルダー
ザ・グラン考える「余白について」
完成しつくされた空間も素晴らしいですが、建築はどこか余白があることも重要だと考えます。
余白があることで、そこにアート作品を飾れたり、お気に入りの照明を置くこともできます。
「余白=無駄」ではなく、「余白=余裕」ととらえています。
心にも余裕が必要なように、建築でも余白という余裕をつくります。つくることで住まう人の個性が現れ、それにふれる、または育むことで、より豊かな生活になると考えています。
余白は腕の見せどころ?
右上の写真は当社のお客様のご邸宅内、中庭を囲む2階の廊下です。
廊下としてはかなり広く、椅子とテーブルさらにテーブルランプまで設置しています。。窓枠は木製で、手前に置かれたオリーブの木が廊下を華やかにしています。
この廊下は単に回遊性、利便性を高めるためだけではなく、生活の余白として、歩く以外の何かを意識した廊下です。もう少し言うと中庭に向き合い長居したくなるようなスペースになっています。
深く座れる椅子にゆったりと座りながら、ランプの明かりで読書をすることもできます。多忙な生活の合間に、お気に入りの椅子でちょっと一息いれる。そんな日常生活シーンが想定しています。
家の間取りでまず考えるべきことは「このスペースは何のためにあるのか?」という使用目的です。しかし、その使用目的のなかに「中庭を見ながら、ゆっくり休むところ」というのを打ち立てることはなかなか勇気がいるかもしれません。
このような空間は生活上の利便性・実用性から考えると、使用目的未満、無駄以上のスペース・空間ですが、「余白」として設計に組み込んでいくことも設計士の腕の見せどころひとつです。
この余白が、生活のゆとりを演出し、豊かさと満足感をもたらし、さらには建築物としての美しさにもつながっていくことは、とてもよくあります。
余白、ゆとり、美しさ、これら共通して上質な空間を生まれるための必要条件として、施主様と共感できる空間づくりのお手伝いをしていきたいと考えてます。

自己と他者との出会いによって開く出来事の空間(芸術的視点から)
(引用元:余白の芸術 李禹煥 みすず書房 p3-4 余白の芸術)
アートは詩であり批評であり、超越的なものである。
そのためには2つの道がある一つ目は、自分の内面的なイメージを現実化する道である。二つ目は、自分の内面的な考えと外部の現実とを組み合わせる道である。
<中略>
私の選んだのは二つ目の、内部と外部が出会う道である。そこでは私の作る部分を限定し、作らない部分を受け入れて、お互いに浸透したり、拒絶したりするダイナミックな関係を作ることが重要なのだ。この関係作用によって、詩的で批評的でそして超越的な空間が開かれることを望む。
私はこれを余白の芸術と呼ぶ。
ところで私は、いろいろな画家の絵面の中にみられるような、ただ空いている空間を余白とは感じない。そこには何かのリアリティがかけているからだ。例えば、太鼓を打てば、周りの空間に響きわたる。太鼓を含めてこのバイブレーションの空間を余白と言う。
<中略>
例えば自然石やニュートラルな鉄板を組み合わせて空間に強いアクセントを与えると、作品自体というより、あたりまで空間が密度を持ち、そこの場所が開かれた世界として鮮やかに見てくる。
だから描いた部分と描かない部分、作るものと作らないもの、内部と外部が、刺激的な関係で作用し合い響きわたるとき、その空間に詩か批評そして超越性を感じることができる。
芸術作品における余白とは、自己と他者との出会いによって開く出来事の空間を指すのである。
李禹煥は「芸術作品における余白とは、自己と他者との出会いによって開く出来事の空間」と言っていますが、私たちの一般的な生活の中における余白とも置き換えられそうです。生活の余白があることで出会えた人やモノ、出来事などなど、そしてその中に大切なものもたくさんありそうです。そう考えると余白がかけがえないものとして、実感がわいてきます。
自分と全然関係ないものを生み出す(音楽的視点から)
(引用元:ひとつの音に世界を聴く 武満徹対談集 晶文社 p231 <1967年6月「現代詩手帖」掲載>)
【詩人、批評家、東京芸術大学名誉教授の大岡信氏と日本を代表する現代音楽家、武満徹との対談】
武満:
書くべき内容を持っている詩人は一流じゃないと思うんだ。書くべき内容を持っているやつがいっぱいいるから、詩人がいっぱいいるわけだな。(笑)本当の詩人はそうじゃないと思う。そうだとしたらつまらないな。
大岡:
一つ一つの言葉が三六〇度の方向を持っていて、どう転ぶかわからない言葉を一つ一つつなげていくんだから、方向なんか出てくるわけがないんだよ。
武満:
ぼくが詩を読んでまず感じることは余白ですよ。ああいうものは他にはない、余白が凄いんだから。あれでぼくはいつも感じるのはプールだな。言葉の並べ方でも、たいへん工夫している人がいて、まず最初それを見て楽しいときがある。しかし、それは永続きしないで、そのあと印刷された文字の上で、かたちなんかを見て楽しんだり、中江さんの詩みたいに残酷な感じがしたりすることがある。最後には白い紙の水面をポンポンポンポンと言葉が飛ぶような……
大岡:
幸福感というのは、結局そういう詩がかけたときにしかないな。自分と全然関係ないものをそこで生み出したとき。人間は自分でなくなる瞬間がいちばん幸福で、だから死ぬ瞬間は以外に幸福なのかもしれない。(笑)
武満:
詩の余白は、そういう幸福と残酷な面をもっている。
<中略>
武満:
詩人の仕事というものは、言葉をどういうかたちにしろ、非常にいいで合わせ方をさせるというか、出会いの環境を設定するに過ぎない。
日本の代表的な作曲家の武満徹が大岡信の詩を見て、その余白に圧倒されるという。もはや余白は何もない空間ではなく、そこに大きな存在感を感じていることがこの対談で感じ取れます。そして余白の意味を人知をこえた、まったく別次元のものが生まれる場のように大岡がとらえています。余白に普段まったく意識していないような可能性を感じる対談です。
余白の美学(美術的視点から)
(引用元:日本人にとって美しさとは何か 高階秀爾 筑摩書房 p165-166 余白の美学)
「余白」という言葉は英語やフランス語には訳しにくい。西洋の油絵では、風景画でも静物画でも、画面は隅々まで塗られるのが本来であり、何も描かれていない部分があるとすれば、それは単に未完成にすぎないからである。だが例えば長谷川等伯の<松林図>においては、強い筆づかいの濃墨の松や靄のなかに消えていくような薄墨の松がつくり出す樹木の群のあいだに、何もない空間がおかれることによって画面に神秘的な奥行きが生じ、空間自体にも幽遠な雰囲気が漂う。また、大徳寺の方丈に探幽(狩野)が描いた<山水図>では何もない広々とした余白の空間が、あたかも画面の主役であるかのように見るものに迫ってくる。
高階秀爾は、探幽(狩野)が描いた<山水図>に、もはや上の武満と大岡の対談の中での余白に存在感を感じるというどころか、「神秘的な奥行き」「空間自体にも幽遠な雰囲気」さらには、それが画面の主役とさえ言っています。日本古来からその美的センスにこのような余白についての強い意識があることは興味深いです。そんな日本人の余白についての美意識の延長で素敵な余白(住まいでも、生活でも、生き方でも)について考えてみたいものです。
「ザ・グラン」は岐阜県と愛知県をメインにハイエンドな高級注文住宅を展開している一級建築士事務所です。「美しい住まい。上質な暮らし。」をコンセプトに専属職人と大工による自社施工の家づくりをしています。
ザ・グランの建てる家は「高級注文住宅に類するけれども、いわゆるゴージャスの延長にある高級感ではなく、素材やゆとりのある空間設計にこだわった品性を感じる家」。
「本当に価値ある住まいとはなにか?」を探求し続けるザ・グラン若原代表の建築への思い、本物へのこだわりに共感し、高級注文住宅の新しいあり方について考えるため、Zenken株式会社レジデンス編集チームが当サイトを立ち上げました。
岐阜の恵まれた自然環境の中、若い感性で豊かな暮らしの本質を追求する「ザ・グラン」のご協力をえて、「本当に価値ある住まい」について探っていきます。
(本サイト名「○△□ 岐阜の高級注文住宅」は禅僧の仙厓義梵が描いた「○△□」<出光美術館蔵>に感じる単純さ、ユニークさ、本質志向、自由さなどのイメージにちなんでいます。)